この記事でご紹介する「ライトハウス」は、2019年に公開されたスリラー映画。孤島の灯台で数週間二人っきりで働くことになった灯台守の男たち。逃げ場のないこの状況で、二人だけの関係性が徐々に煮詰まって行く狂気の様子を描く。
新任の若い灯台守をロバート・パティンソン、先任のベテラン灯台守をウィレム・デフォーが演じる。
この映画を観るか迷っている方は、後でご提案する ”ジャッジタイム” までお試し視聴する手もあります。これは映画序盤の、作品の世界観と展開が ”見えてくる” 最短のタイミングのことで、作品が気に入らなかった場合に視聴を離脱する目安タイムです。
もし、この映画が気に入らなかった場合でも、このジャッジタイムで観るのを止めちゃえば時間の損切りができます。タイパ向上のための保険みたいなものです。
この映画を初めて観る方のことも考えて、ネタバレなし で、作品の特徴、あらすじ(ジャッジタイムまでに限定)、見どころを書いて行きます。この映画の予習情報だとお考えください。
この映画を観るかどうか迷っている人、観る前に見どころ情報をチェックしておきたい人 のことも考え、ネタバレしないように配慮しています。
全編、孤島の灯台かその周辺のみが舞台、そして映像は白黒スタンダード・サイズというこだわりぶり。ハッキリ言って息苦しさしか感じないこの異様な作品を、丸腰でご覧になって「思ってたのと違う」と後悔しないように、この記事で少し予習して行きませんか?
ジャッジタイム (ネタバレなし)
この映画を観続けるか、見限るかを判断するジャッジタイムですが、
- 上映開始から20分00秒のタイミングをご提案します。

この辺りまでご覧になると、この映画の音と映像のテーストが掴めると思います。ただし、ここに至る以前に「無理だ」と感じたら潔く撤退することをおススメします。内容的には、20分ぐらいまでご覧になると、主人公の2人が置かれた状況、2人の関係性が見え始める頃なので、この観点でも好き嫌いの判断が付くと思います。
概要 (ネタバレなし)
この作品の位置づけ
「ライトハウス」(原題:The Lighthouse) は、2019年公開のスリラー映画。19世紀末の孤島を舞台に、全編に渡って島内の灯台とその周辺のみで物語が進行するワンシチュエーション映画。
この島に住み込みの灯台守として派遣される、先任のベテラン灯台守をウィレム・デフォー、新任の新人灯台守をロバート・パティンソンが演じている。
全編白黒映像、画角もスタンダード・サイズという異質なフォーマット。この灯台守の男2人が、交代の別ペアが来るまでの4週間の間、上司部下の主従関係の中で次第にその関係性が煮詰まって行く様子を描く、非常に息苦しい作品。
制作・配給
脚本は、監督も務めたロバート・エガースと、その弟のマックス・エガースによる共同執筆。ロバート・エガースにとっては、「ウィッチ」(2015年) に引き続く長編監督2作目にあたる。
本作は、灯台守について書かれた資料や書物を参考にエガース兄弟が脚本を執筆したが、特に1801年にウェールズのスモールズ灯台で実際に起きた、相棒と不仲に陥った灯台守が精神的に支障を来したという悲劇的な事件に強くインスパイアされたと言われる。
なお、「ウィッチ」も本作「ライトハウス」(2019年) も、インディペンデント系映画会社A24(エートゥエンティフォー)が配給を担っている。
評価
Rotten Tomatoes(ロッテン・トマト)では、90%とこの上ない支持率を得ている(Rotten Tomatoesでは60%以上が『新鮮』、60%未満が『腐っている』という評価)。そして総評においても、”見事に映像化され、パワーハウスとパフォーマンスの組み合わせに導かれた魅力的な物語である『ライトハウス』は、ロバート・エガースの格別な才能をもつ映画作家という評価を確立した” と、評されている。
ウィレム・デフォーとロバート・パティンソンの2人の演技(パフォーマンス)を、灯台(ライトハウス)と韻を踏みながら、Powerhouse(パワーハウス)とPerformance(パフォーマンス)と表現している。
商業的成果
この映画の上映時間は1時間49分と、標準的、もしくは標準よりやや短めである。しかし、陰鬱な映像と息苦しいストーリー展開により、体感的には相当長く感じると思う。そして、製作費は非公開であるが、世界興行収入は1千8百万ドルを売り上げたとされる。
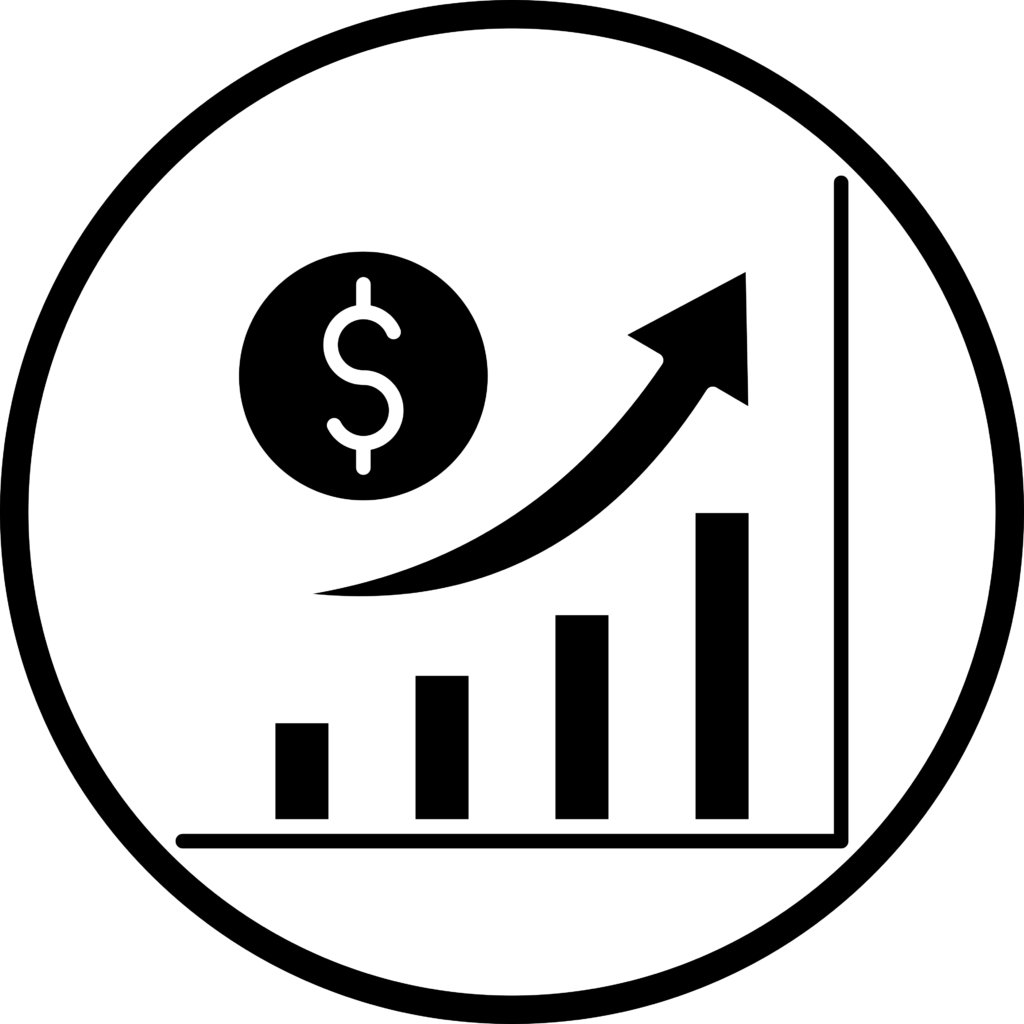
この重苦しい趣味的な映画が、1千8百万ドルも売り上げられたのは、ロバート・パティンソンとウィレム・デフォーのネームバリューに依るものだろうか。
あらすじ (20分00秒の時点まで)
ニューイングランド州に属す大西洋上の孤島。ここは周囲の波も荒く、島というより岩礁に近い。ただしここには灯台が一つ設置されており、19世紀のこの時代においては、2人一組がチームとなって、4週間交代でこの灯台に住み込みながら灯台守の任務に就いていた。
今日から4週間任務に就くのは、足の悪い初老のベテラン灯台守(ウィレム・デフォー)と、今回が初めての灯台守の任務となる新人(ロバート・パティンソン)である。初老(ウィレム・デフォー)とコンビを組んでいた前任者が死んだので、その補充として新人(ロバート・パティンソン)が採用されたのだ。
2人は往路も含めてろくに言葉を交わすこともなく、島に着いても先任の2人と挨拶もしない。ただ宿舎の最上階の寝室に私物を運び込む。
新人は、自身のベッドのマットレスの中に、小さな木彫りの人魚の人形が埋め込まれているのを見つけ不思議な気持ちになる。期せずして初老が言うには、亡くなった前任者は人魚の幻影に惑わされるようになって死んだとのこと。
最初の晩の夕食時に明らかになったことは、初老は非常に高圧的な態度で部下の新人に接してくること。そして、業務も理不尽なほどに不公平に分担する。新人がそれは規則違反だと反駁しても、ここでは俺が規則だと初老は押し切ってくる。
特に初老は、灯台の最上階にある灯室内の業務は自分が独占し、新人には灯室に足を踏み入れることすら許さない。さらに、足が不自由な初老は肉体労働は一切せず、貯水槽の掃除、石炭の補充、灯油の運び込みといった全ての重労働が新人の割り当てとなる。
新人は、新たな働き口を求めてこの灯台守の仕事に就いたばかりであり、かつ自身の業務評価は、上司の初老が日々付ける日誌の内容で決められてしまうため、新人は初老に従うしかない・・・
これからの4週間弱、逃げ場のないこの小さな島で暮らすことになった新人と初老。2人は果たして良好な関係を築くことができるのだろう…?
見どころ (ネタバレなし)
この映画の見どころを3つの観点で書くことにチャレンジしてみたいと思います。ただし、本作品は非常に特異な作風なので、こういう特徴の映画なので覚悟して観てくださいねという事前予告的な内容に近くなります。
いずれにせよ、ネタバレは無しで書いていきますのでご安心ください。
演技、演技、演技
初老の灯台守に扮するウィレム・デフォーと、新人の灯台守に扮する(ロバート・パティンソン)の演技が凄いです。
というか、この映画には正味この2人しか出て来ません。よって、ひたすらこの2人の演技を堪能する他ありません。
なので、映画作品でありながら、舞台の二人芝居を観劇するような感覚に近いかも知れません。2人の鬼気迫る演技をウンザリするまで楽しんでください。
独創的な世界観
画面は白黒で、画角もノンワイド。そして、孤島をぐるりと囲う外海の荒波の音、吹きすさぶ海風の音、灯台が定期的に発する警告音、更に、そこに全編に渡って不穏なBGMが重なってくる。『独創的な世界観』なんてチープな表現では言い表せない作風となっています。
『陰鬱』なんて表現を飛び越して、息苦しさしか感じない作品なのですが、皆さんの目にはどう映るでしょうか?
解釈の余地
非常に多くの解釈の余地が残される作品です。その余地は、皆さんのが想像力を駆使して埋めて行くしかありません。
物語は基本的に、部下である新人(ロバート・パティンソン)の主観で描かれて行きます。そして、新人の視座で上司である初老の灯台守(ウィレム・デフォー)と、2人の関係。特に新人が上司に抑圧される様子が描かれて行きます。
そこに、前任の灯台守の死の謎。時折メタファーとして扱われるカモメが挿し込まれます。
そして、根底には人魚伝説も絡まってきたり。神話のような光景がフラッシュバックのように挿入されたり・・・
どこまでが新人(ロバート・パティンソン)が実際に目にした光景で、どこからが彼の夢や幻覚なのか、その境界線が我々観客からは判別が付かなくなっていきます・・・
こうして解釈の余地がどんどんと膨らんで行きます。
まとめ
いかがでしたか?
必要最小限の情報で、この映画の独特の立ち位置をお伝えすることが出来ていると嬉しいです。
この作品に対する☆評価ですが、
| 総合的おススメ度 | 2.5 | 何をどう楽しめば・・・ |
| 個人的推し | 2.5 | 何故か飽きないのは事実 |
| 企画 | 4.0 | 目の付け所は面白い! |
| 監督 | 2.0 | 難解にすることを目的化してる? |
| 脚本 | 2.5 | 起伏は無い |
| 演技 | 4.5 | 2人の演技は神がかり的 |
| 効果 | 3.0 | 画の陰影は凄い |
このような☆の評価にさせて貰いました。
映画を”何がしかを楽しむもの”と定義するならば、この作品は正直評価のしようがないと思います。それぐらい個性的です。ただ一つ驚いたのは、不思議と退屈しない点です。登場人物2人の演技が凄くて、ずっと観ちゃいます。
好き嫌いは極端に分かれる作品だと思います。
 あわわっち
あわわっち何を描きたいのか解らないというより、何も描く気が無いことが判ったという感想


